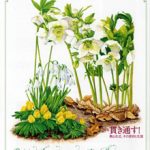連載 伝わる言葉で伝える福音 第7回 聖書にそう書いてある?
青木保憲
1968年愛知県生まれ。小学校教員を経て牧師を志す。グレース宣教会牧師、同志社大学嘱託講師。映画と教会での説教をこよなく愛する、一男二女の父。
聖書については、もう少しこだわってみたい。
宗教二世牧師の私は、この「聖書」にとても悩まされてきた。事あるごとに「聖書にそう書いてある」と言われ続けてきたからである。言い返したくても言い返せない―。そんなジレンマを抱えてきた。
私たちの思考法に「演繹的」「帰納的」というものがある。「演繹的」とは、はじめに物事を「こうあるべし」と捉え、その前提から目の前の出来事を判断するやり方である。一方「帰納的」とは、目の前の出来事を積み重ねる中で、物事は「こう考えるべき」というルールを作り上げるやり方である。
たとえば、毎日あなたに異性から花束が届けられるとしよう。二人が夫婦や恋人同士であるなら、届けられる花束は「愛の証し」となる。だからあなたは「明日もきっと花束が届くだろう」と思うことができる。これが演繹的な思考法である。
一方、その異性とあなたはまだ特別な関係ではないとしよう。あなたは毎日届けられる花束を見て、一つの結論に達する。「あの人は私のことが好きに違いない」と―。これが帰納的な思考法である。
一般的に私たちは、「帰納的」思考で世の中を生きている。しかし一度クリスチャンになると、真逆の「演繹的」思考に価値を見出すようになる。「はじめに神ありき」の前提でこの世界を見直すからだ。生じるすべての出来事は神の管理下に置かれていて、聖書という「ルールブック」を通してのみ私たちは事の是非を知ることができるようになる。
そして、神の管理下では起こり得ないはずの出来事が万が一生じた場合、それはそう思ってしまう私たちの未熟さゆえと受け止めるよう教えられる。あくまでも「演繹的」に立つ姿勢を崩さない、否、崩せないのである。
しかし多くの人にとって、この考え方は承服しがたい。なぜなら前提となる「神ありき」が、彼らの中には存在しないからだ。
例を挙げよう。私と友人は共に教会に通い、そして大学受験をした。彼は真面目に諸集会に出席し、奉仕にも熱心だった。一方、私はと言うと、礼拝を休んで塾に通う始末。しかし私が合格し、彼は落ちた。
私は不思議に思った。なぜなら教会の牧師は何度も「神様の前に忠実な者こそ祝福を受ける」と聖句を用いながら語っていたからだ。
落ちた彼は牧師に尋ねた(と聞いている)。「どうしていい加減な青木君が合格して、神様の教えを守って来た私が落ちたのですか?」と。そして最後にこう付け加えた。「先生、聖書にそう書いてあるんでしょ?」
「聖書にそう書いてある―」
これは神様をまだご存じでない方にとって、ある種暴力的な言い回しである。同じ前提(神ありき)を共有できない場合、この言葉を言われた瞬間に会話が成立しなくなってしまう。ついていけなくなるのである。
私たちは「聖書にそう書いてある」と語る代わりに、その聖句を受け止めて生きている私たちのリアルな語り(ナラティブ)を他者に伝えるべきである。聖句に裏打ちされた私たちの生きた言葉を通してのみ、聖書は「生きづらい世の中を生き抜くための知恵の書」として人々に伝わっていく。
私たちは、自分の話が「演繹的」に偏っていないか、独りよがりに陥っていないか、常に吟味する必要がある。「帰納的」に生きている多くの人に対し、「演繹的」な信仰的世界観をいきなり押し付けていなかったか?
むしろ私たちは、聖書の言葉を受け止めて生きることの素晴らしさを、自分の言葉と生活を通して「帰納的」に伝える必要がある。「聖書にそう書いてある」ではなく、「聖書の言葉を通して生きている私たちの語りかけ」こそ、「伝わる言葉で伝える福音」そのものである。